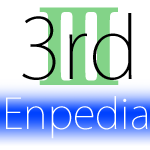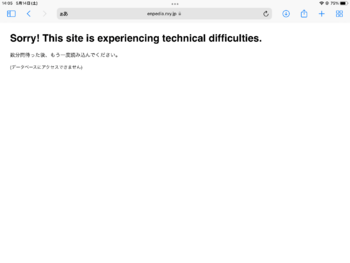エンペディア
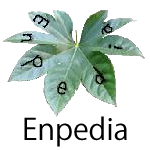 | |
| エンペディアのロゴ「ミヤコ様」 | |
| 開設 | 2009年4月21日(1st),2010年11月30日(2nd),2013年1月1日(3rd) |
|---|---|
| ウィキシステム | MediaWiki |
| 分野 | 謎の百科事典もどき[注 1] |
| 言語 | 日本語 |
| サーバー所在国 | 日本(Sakura) |
| 使用時刻 | 日本標準時(JST) |
| 現状 | 記事増加中 |
| 創設者 | オレリ |
| 運営者 | Enpedia:スタッフで規定された最上位スタッフ |
| ライセンス | CC BY-SA 3.0 |
エンペディア (Enpedia) は、誰でも利用できる "謎の百科事典もどき" のウェブサイト。今、あなたが見ているサイトである。
ウィキペディアと同じ「MediaWiki」というシステムを使っているためサイトの構造がよく似ているが、姉妹サイトやパクリサイトではない。ウィキペディアの姉妹プロジェクトではないため、ウィキメディアでもない。
むしろ、「ウィキペディア」や「アンサイクロペディア」といった、これまでの百科事典サイトと異なる方向性を模索することを目的としている[1]。
概要[編集]
方針の特長[編集]
ルールが厳しくて幅広い情報を自由に扱えない「ウィキペディア日本語版」を反面教師としており、分かりやすさと自由気ままをモットーとしている。その一方、自由すぎるあまり、無断転載・誹謗中傷・荒らしがはびこってしまった「ユアペディア」の二の舞にならないよう、最低限の管理体制を整えている。
ルールが最低限しか存在せず、自由な発想で記事を執筆してよいのが特長。他サイトと異なり「スタブ」という概念もないため、短めの記事を気軽に書くこともできる。
そのためか、他サイトから漂流してきたユーザーが比較的多い。ま、便宜上某映画のセリフを借りるが、そもそも大手サイトに無縁なはぐれ者、一匹狼、変わり者、オタク、問題児、鼻つまみ者、厄介者、学会の異端児、そういった人間の集まりだ。気にせず好きにやってくれ。
名前について[編集]
「エンペディア」という名前の由来は定かではないが、現在の関連文書の公式発表では「百科事典」を意味する英単語「Encyclopedia(エンサイクロペディア)」の略であるとされている。
当初は、アンサイクロペディア内で創作された架空のウィキサイト「エンサイクロペディア」[注 2]が元ネタと言われていた。実際に、旧ロゴマークは「エンサイクロペディア」のロゴの改変であった。創設者が失踪して真意が不明となった後に、残されたユーザーたちが議論を行い、「百科事典の略」という説が正式採用されることとなった。
略称・通称は「EP」「印」など。「印」は字形が「EP」と似ていることに由来するが、用いている人は少ないどころが滅多に見ない。
特色[編集]
記事[編集]
アニメ・ゲーム・声優などのサブカルチャーと、サッカー関連の記事が抜きん出て多く、次いでMediaWiki関連の記事が多い。2021年からは鉄道関連、2022年からは日本史関連の記事も増加している。特定分野の記事が多い一方で、基本的な単語でも記事が存在しなかったり、短めの記事が多かったりと不揃いである。ウィキペディア・アンサイクロペディアと違って「スタブ」という概念が存在しておらず、短い記事でも気軽に作成できるのが特長。「一行記事」も許容されることが多い。
中身が充実した「長い記事」もないわけではない。例えば「交流」のように、ウィキペディアよりも内容が充実した学術系の記事もある。理系の記事が充実している一方で、マイナーな歴史上の人物の記事も多い。
「エンペディアにおける長い記事」も参照
「このスタイルで投稿しなければならない」という決まりは無く、自由な形式で投稿された記事が多い。個人の感想が書かれていたり、アンサイクロペディアみたいな冗談で書かれた記事も多々ある。また、出典の記載が必須ではなく、独自研究も認められている。独自研究に基づいた記事の数々はウィキペディアと比べて深みがある[不要出典]。
「エンペディアにおける記事のスタイル」も参照
残念ながら、日本語がこなれておらず、読みにくい記事も少なくない。
ロゴマーク[編集]
「ミヤコ様」も参照
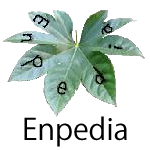
ヤツデの葉に「Enpedia」と書き込まれた写真をロゴとして用いており、これを「ミヤコ様」と名付けている。
旧エンペディア時代(2010年以前)には、ジグソーパズルのピースをさいころの5の目の形に並べたロゴマークを用いていたが、これはアンサイクロペディア内の記事『エンサイクロペディア』で使われていた画像の改変であった。著作権上の問題があるため、サイト移行時(後述)に現在のものを採用するに至った。移転前の旧エンペディア跡地では、現行のロゴマークを枯葉の姿に変えて表示している。
3rd Enpedia始動時2nd Enpediaのロゴをそのまま引き継ぐのではなく新たに決め直すことになり、正式なロゴが決定するまではrxyによる暫定のロゴが使われた。フォーラム:ロゴの決定の議論の結果2013年11月1日に2ndに引き続きミヤコ様をロゴマークにすることが決定し、2014年1月1日に反映された。
役職[編集]
「スタッフ」という、役職が存在する。スタッフは、運営上の問題を解決するために特殊な操作を行うことができる。具体的には、ウィキソフトウェアの設定変更、データベースへのアクセス、チェックユーザー[注 3]など、エンペディアの運営に大きな影響力を持つものである。一般ユーザーからの立候補・推薦は受け付けていない。
2010年のサイトリニューアル前後に設けられた役職であり、当初は「上級スタッフ」「一般スタッフ」「技術スタッフ」「運営スタッフ」「特別スタッフ」と部門が細かく分けられていた。現在は統合が進み「最上位スタッフ」「上位スタッフ」「一般スタッフ」の3区分となっている。またかつては、データベース運営者専用の「ウェブマスター」、設立者であるオレリ氏専用の「創設者」といった役職が存在していたが、これらもすべて「スタッフ」に統合されている。
他の特徴的な役職には「閲覧者」がある。これは、閉鎖済みの旧エンペディア跡地を閲覧できる権限である。閲覧は可能だが、編集行為は基本的に禁止されている。[2]
歴史[編集]
「Enpedia:最近の出来事」、「Enpedia:過去の出来事」も参照
初代 (1st Enpedia)[編集]
ウィキペディアやアンサイクロペディアに居心地の悪さを感じていたオレリ氏が、隠れ家的存在として開設した。2009年4月21日に最初のエンペディア(1st Enpedia)が myht.orgドメイン[注 4]にて設立される。同年の8月9日[注 5]に正式に公開されたとされる。アンサイクロペディアの削除主義者が流入してくることを恐れて、宣伝をほとんどしなかったため、ユーザーが全く増えない「過疎ペディア」であった。
8月12日頃、外装(スキン)にエラーが発生し、一か月ほど「プロトタイプ・エンペディア」なるものが設置されたらしいという伝説がある。ただし、もはや当時の利用者など誰も残っていないので、当時の詳しい事情は知る由もない。
当初は、MediaWiki の実験のために設立された「個人サイト」という色合いが強かった。また、有料会員しか編集できない「ニコニコ大百科」の代わりを確保したり、アンサイクロペディアでの活動疲れ(ネタの枯渇)から休養したりという目的もあったと言われている。しばらく経過した後、他サイトで削除されつつある有用な記事の回収や、それらに補足を行うという実用的な方向性が(おぼろげながら)定められた。
しかし、同年8月12日から大規模なスパム攻撃の被害に遭う。翌年の2010年2月8日には、管理者以外の編集・アカウント作成を一切禁止する措置が取られた。オレリ氏は、一時はエンペディアの閉鎖も考えていたが、結局6月16日に8名のユーザーに管理者権限を付与。運営を半ば押し付ける形でバトンタッチし、自らは活動を停止した。この時も大規模なスパム被害は継続しており、任命された管理者たちは多くのページに1つずつ半保護処置(未登録ユーザーの編集を禁止する処置)を行うという苦労の掛かる作業に追われた。なお、このスパムは未だに出現することがあるという。
最初期は、運営者の一存で管理者権限の付与が行われていた。(かつてのアンサイクロペディアで「お札降り型」と呼ばれたものに相当する)。ユーザーの投票による任命制度が制定されたのは、2010年頃になってのことである。この頃から、具体的な方針について議論が重ねられるようになり、サイトの運営方法が徐々に固まって行った。
2代目 (2nd Enpedia)[編集]
オレリ氏の活動停止からしばらく経ち、残された管理者の一人 rxy氏(当時は Hosiryuhosi)がサイト運営を後継する運びとなった。サイトの詳細設定はオレリ氏しかアクセス・操作できず、このままでは永続的な運営は難しいため、クローンサイトを新たに立ち上げることとなった。
2010年11月30日、1st を複製した新たなエンペディア(2nd Enpedia)が設立された。初代エンペディア跡地は編集禁止措置が取られ、新たな運営者が「ウェブマスター」という役職に就いた。[3]「スタッフ」という役職が制定されたのはこの時である。この頃のスタッフは、ウェブマスターを補助するという位置づけであった。[3](前述の通り、現在は「ウェブマスター」も含めて全て「スタッフ」に統合済み。)[3]
なお、2011年7月4日には、偽物のエンペディア(enpedia1.myht.org)が設立されていたことが発覚したが、現運営者の通報を経て myht.orgの管理者による閉鎖処置がとられている。[4]
2011年に入って、創設者オレリ氏が活動を再開。[5][6]彼には「創設者」という役職が与えられたが、[7]これは具体的な権限をもたない「名誉職」であった。「rxy 氏にエンペディアの全権限を移譲する」という宣言をオレリ氏が行い、名実ともに新たな体制下での運営が始まった。[8]
「個人サイト」時代のエンペディアは著作権がそれほど意識されておらず、ゲームキャラクターの画像などがアップロードされていた。そうした著作権侵害状態を一掃するために、再度、新たなエンペディアを一から立ち上げることが決定。rxy 氏が、初代~3代目まで全エンペディアの運営者となる運びになった。rxy.jp ドメインへの完全移行や、初代~3代目までのデータベース共有化・統一ログイン導入が決定したのもこの時である。様々な運営方針が合意によって正式化され、CCライセンス(CC-BY-SA 3.0 Unported)の採用もようやく正式決定した。(それ以前は「ライセンス不明」の状態であった。)
2012年末頃から段階的に移行作業が進められた。まずは、CCライセンスに同意するユーザーのみが編集に携わった記事の移行作業(インポート)が進められた。12月26日に、3rd_Enpedia 初の記事となる「アンチリテラルの数秘術師」(2nd からのインポート)が作成された。[9]
現エンペディア (3rd Enpedia)[編集]
2013年[編集]
2013年1月1日、ついに3代目への完全移行が果たされ、2代目以前のエンペディアは閉鎖された。
当初、rxy.jp ドメインはmyht.orgの独自ドメイン設定によるものだったが、2013年4月6日には運営者の所有するVPSへと移行した。これによって、エンペディアの表示速度は格段に向上した。
9月30日には、インポートの方針が改訂された。それまでは、編集者全員の同意が取れなかった記事は移行を断念・保留するしかなったが、ここからは移行可能な箇所だけを部分的に移行する処理(切り捨てインポート、編集インポート)が進められるようになった。
当初、初代・2代目エンペディアは「enpedia.rxy.jp/1st/」及び「enpedia.rxy.jp/2nd/」にデータベースが置かれていたが、2013年11月9日にEnpedia 1stのデータベースが削除され、Enpedia2ndのデータベースはold-enpedia.rxy.jp(サブドメイン形式)に移動された。[10]
12月14日、管理者などへの立候補・推薦方法を定めた「Enpedia:追加権限保有審査」が正式化された。
2014年[編集]
5月にサーバーメンテナンスが行われたが、ページ数の多さから不具合が発生。些末なカテゴリを一斉整理する運びとなり、結果的に「所属ページ数が5ページ未満のカテゴリは作成しない」ことを定めた「Enpedia:カテゴリの運用方針」が制定された。(なお、カテゴリ名前空間が特別にサーバーへの負荷を高めるわけではない。当時、サーバーを救済する「対症療法」として、優先度の低い些末なカテゴリが整理された。)
8月30日、アクセスカウンタが無効化され、代わりに外部サービスを利用した日次更新アクセス解析が公開される事となった[11]。無効化された理由は、アクセス毎にSQL文が発行され、障害発生時にログの精査が大変になるためである。これ以前は、各記事ごとの閲覧数を確認することが可能であったが、現在ではサイト全体の閲覧数しか確認することしかできない。
11月8日にはポータルの運用が開始し、12月1日には「Enbooks(仮)」(現在の「よみもの」)の試験運用が開始するなど、他の百科事典サイトに見られるような機能が次々と備わり始めた。
11月2日、rxy 氏が「最上位スタッフ」を辞任し、篠田陽司氏に交代した。12月26日には、rxy 氏が最上位スタッフに復帰し、以後「複数人の最上位スタッフ」による運営体制が現在まで続いている。
2015年[編集]
1月、{{スタブ}} が廃止され、{{書きかけ}} に移行された。(後述のとおり、この {{書きかけ}} も2022年には廃止される。)
5月1日、記事数が5,000項目を突破。そこから2カ月も経たない6月24日には、倍の10,000項目に到達した。
12月14日、「ビューロクラット」「チェックユーザー」「オーバーサイト」の条件について定められた。
2016年[編集]
7月8日、「フォーラムもどき:エンペディアは「謎の百科事典もどき」なのか」にて、正式にエンペディアが「謎の百科事典もどき」であることが決定したらしい。正直、どうでもいい議論である
11月23日、エスケープ転載の方針が決定した。
12月8日、「Enpedia:おすすめ項目 (仮)」がスタートした。ウィキペディアの「秀逸な記事」などとは異なり、選考なしで自分の好きな記事をドンドン追加していく方式である。なお、「エンペディアらしさ」とかいうよく分からんものを重視した結果、現在でも「(仮)」がついたままである。外し忘れているわけではない。
2017年[編集]
4月22日、Enbooks(仮)がよみものプロジェクトとして正式リリースされた。が、現在に至っても全く賑わっていない。
9月28日、記事数が20,000項目を突破した。
2018年[編集]
1月1日、現エンペディア設立5周年を迎えた。2代目エンペディアで「CC BY-SAライセンスでの使用許諾」を行っていないユーザーの投稿は、全て切り捨てインポート出来るようになった。(この方針自体は2015年時点で決定済み。)......が、この頃には十分にエンペディアが発展しており、昔の記事など誰も気に留めなかったのか、切り捨てインポートは全く行われなかった。
2月1日には「任意団体Enpedia」が設立された。4月からは自動広告の表示[13]がスタートし、運営資金の充実・透明化が図られた。それ以後の収支は継続的に報告されている。[14]
3月10日、4名のユーザーが相次いで管理者に立候補(Nami-ja、Augustus Caesar、プログラマリオ、Fusianasan1350)。3月24日に全員、管理者に就任した。
3月14日、ホワイトデーのこの日に(転送ページなどを含む)総ページ数が30,000ページに達した。記念すべき30,000ページ目は「大阪タイガース」(転送ページ) 。
この年は、日本の出来事が最も無差別に収集された年であった。
2021年[編集]
4月15日、記事数が50,000項目に到達した。50,000本目の記事は、『ぽけでび 〜ポッケdeびーすと〜』のキャラクターについて解説した「ココア (ぽけでび)」であった。なお、2014年頃にはすでに「ぽけでび」の記事が充実しており、2016年には長いページの2番目に入るほどの文章量であった。2021年に入ってからは、ぽけでび関連の個別記事が充実するようになった。
3月にはエンペディアダービーが開催された。詳しくは当該項目を参照。
詳細は「エンペディアダービー」を参照
4月頃からは、Twitterの鉄道界隈からユーザーが大量に流入。同界隈に関連する記事が急増した。だが、鉄道関連の有識者が多かったのはこれ以前からである。
2022年[編集]
1月頃から、マリオカート関連(通称・MK界隈)の記事が急増する。MK界隈の人物記事が数多く立項された。
2月頃からファイルがアップロード出来ないバグが発生。ファイルの削除・移動もできなくなった。5月11日に不具合が解消し、以後はバグ解消に歓喜したのか不具合以前を上回る勢いでアップロードされるようになった。
2月21日、記事数が6万項目を突破する。60,000本目の記事は「お江戸-O・EDO-」。
7月22日、記事数が7万項目を突破する。70,000本目の記事は「そんな第一話」である。60,000項目から僅か5ヶ月という短さでの達成であった。
5月頃よりサーバーが重くなっていたが、サーバーメンテナンスにより9月1日に解消し、同日はお祭り騒ぎとなる。メール送信ができなくなるバグ、アカウントの作成が不可能となるバグも発生していたが、10月~11月ごろにようやく解消された。
10月頃から「マイクラ戦闘地帯」の記事が急増し、鉄道界隈・マリオカート界隈に次ぐ「第3次・外部流入プチブーム」が到来する。
10月16日、WxYuki氏が作成した「エスケープ転載お助けツール」が公開された。このツールのおかげか、これ以降のエスケープ転載が活発になったような気がする(個人の感想です)。
2015年に {{スタブ}} が廃止され {{書きかけ}} という妙な形で生き残っていたが、2022年11月に {{書きかけ}} も廃止することが決定した[15]。
2023年[編集]
1月1日、3rd Enpedia が設立10周年を迎える。めでたい。
1月頃から、鉄道界隈に続いてバス界隈の投稿も増加。人物記事(Twitterユーザーについての記事)は案の定グレーな感じであるが😅、その一方、車体型式などの記事はクオリティが高い。
さらに新規利用者が増加し、K-POP・広島県・近代イデオロギー論・日本軍についての記事が増加した。
2月14日から2週間ほど、クソデカ寄付のお願いがサイト上部に居座り、全エンペディアンを困惑せしめる。ジミー・ウェールズが悪いよ、ウェールズが~
2月15日には、記事数が80,000本を超えた。80,000本目の記事は「KISS」であったが、誰も気にしなかった。
3月には、みんなで記事を書きまくるイベント「第1回ミヤコ様スーパースプリント」が開催された。(なお、9月には第2回、翌年1月には第3回が開催された。)
3月ごろから「エンペディアの見た目をもっと変えていこうキャンペーン」が敢行され、現在まで不断の取り組みが続いている。じわじわサイトの読みやすさ・使いやすさが向上していると、もっぱらの噂である。
12月31日の大晦日、マスコットキャラクターの「エンペたん」が爆誕する。
2024年[編集]
1月下旬、統計関連の特別ページの仕様が変更された。これまではリアルタイム更新だったが、これ以降は「毎日午前五時ごろ」の定時更新となる。なお、集計処理が重たい一部ページについては、週一の自動メンテナンス時に行われる。
2月4日、ヘッダーに各種SNSへのシェアボタンが追加された。X(旧Twitter)、Facebook、はてなブックマーク、LINEに記事をシェアすることができる。はてブにシェアしてもタイトルの表示がおかしいのは内緒である。
2月24日、リニューアルした「Enpedia:方針」が発効される。それ以前の「Enpedia:方針」は「Enpedia:運用細則」へと改名され、方針の下に属するサブルールという扱いになった。
3月3日、記事数が10万を突破する。だがしかし、3月22日・3月31日に、著作権上の問題があった約3000記事が一斉削除されたため、10万を下回る。4月24日、ふたたび記事数が10万を突破した。
8月31日、全てのスマホユーザーに対して「モバイルビューもどき」ガジェットが有効化され、サイトの見た目が大幅に変化した(参考)。スマホユーザーのアクセスが増えることが期待される。
8月1日〜9月30日にかけて「第0回エンペディア大賞」が開催される。過去10年間に投稿された記事のベスト・オブ・ベストを決める企画で、400件弱の投票が行われた。各部門の上位5件までの記事は下記のとおり。
| 順位 | 記事名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 意外な物の名前 | 8票 |
| 2位同率 | 2024年の鉄道 | 7票 |
| 〃 | 2023年の鉄道 | 〃 |
| 〃 | 過疎ペディア | 〃 |
| 5位 | 飯塚事件 | 6票 |
| 順位 | 記事名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 最寄駅 | 5票 |
| 2位同率 | いかがでしたかブログ | 3票 |
| 〃 | 曖昧さ回避 (曖昧さ回避) (曖昧さ回避) | 〃 |
| 〃 | 剽窃 | 〃 |
| 5位同率 | 出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』 | 2票 |
| 〃 | 一覧の一覧の一覧の一覧 | 〃 |
| 〃 | 知っておこう | 〃 |
| 〃 | たらい回し | 〃 |
| 〃 | Windowsの準備をしています | 〃 |
| 〃 | エンペディア帝国 | 〃 |
| 順位 | 記事名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1位同率 | 居住確認のお伺い | 4票 |
| 〃 | 日本全国の銘菓 | 〃 |
| 3位同率 | モネの池 | 2票 |
| 〃 | 特色のあるファミリーマートの店舗 | 〃 |
| 〃 | もしもシリーズ | 〃 |
| 〃 | 海のギャング | 〃 |
| 〃 | 中川かのん | 〃 |
| 〃 | クラシック音楽の曲名の俗称の一覧 | 〃 |
| 〃 | 春日俊彰の所沢フレンドリーパーク | 〃 |
| 〃 | (^ ^) | 〃 |
記事数の推移[編集]
| 総記事数 | 達成日時 | 前回からの期間 | 増加ペース |
|---|---|---|---|
| 500 | 2013/6/23 | 179日[注 6] | 2.8 記事/日 |
| 1,000 | 2014/2/2 | 224日 | ▼2.2 記事/日 |
| 1,500 | 2014/6/23 | 141日 | ▲3.5 記事/日 |
| 2,000 | 2014/9/7 | 76日 | ▲6.6 記事/日 |
| 3,000 | 2014/11/13 | 67日 | ▲14.9 記事/日 |
| 4,000 | 2015/1/18 | 66日 | ▲15.1 記事/日 |
| 5,000 | 2015/5/1 | 103日 | ▼9.7 記事/日 |
| 6,000 | 2015/5/14 | 13日 | ▲76.9 記事/日 |
| 7,000 | 2015/5/26 | 12日 | ▲83.3 記事/日 |
| 8,000 | 2015/6/4 | 9日 | ▲111.1 記事/日 |
| 9,000 | 2015/6/16 | 12日 | ▼83.3 記事/日 |
| 10,000 | 2015/6/24 | 8日 | ▲125 記事/日 |
| 17,000[注 7] | 2016/11/8 | 503日 | ▼13.9 記事/日 |
| 18,000 | 2017/2/14 | 98日 | ▼10.2 記事/日 |
| 19,000 | 2017/6/11 | 117日 | ▼8.5 記事/日 |
| 20,000 | 2017/9/28 | 109日 | ▲9.2 記事/日 |
| 21,000 | 2018/1/13 | 107日 | ▲9.3 記事/日 |
| 22,000 | 2018/3/15 | 61日 | ▲16.4 記事/日 |
| 23,000 | 2018/5/4 | 50日 | ▲20 記事/日 |
| 24,000 | 2018/7/10 | 67日 | ▼14.9 記事/日 |
| 25,000 | 2018/9/18 | 70日 | ▼14.3 記事/日 |
| 26,000 | 2018/11/15 | 58日 | ▲17.2 記事/日 |
| 27,000 | 2018/12/27 | 42日 | ▲23.8 記事/日 |
| 28,000 | 2019/2/16 | 51日 | ▼19.6 記事/日 |
| 29,000 | 2019/3/30 | 42日 | ▲23.8 記事/日 |
| 30,000 | 2019/4/30 | 31日 | ▲32.2 記事/日 |
| 31,000 | 2019/6/8 | 39日 | ▼25.6 記事/日 |
| 32,000 | 2019/7/24 | 46日 | ▼21.7 記事/日 |
| 34,000[注 8] | 2019/10/31 | 99日 | ▼10.1 記事/日 |
| 35,000 | 2019/12/24 | 54日 | ▲18.5 記事/日 |
| 36,000 | 2020/2/11 | 49日 | ▲20.4 記事/日 |
| 38,000[注 9] | 2020/4/14 | 63日 | ▼15.8 記事/日 |
| 39,000 | 2020/5/13 | 29日 | ▲34.5 記事/日 |
| 40,000 | 2020/6/16 | 34日 | ▼29.4 記事/日 |
| 41,000 | 2020/8/9 | 54日 | ▼18.5 記事/日 |
| 42,000 | 2020/9/28 | 50日 | ▲20 記事/日 |
| 43,000 | 2020/10/30 | 32日 | ▲31.2 記事/日 |
| 44,000 | 2020/11/22 | 23日 | ▲43.5 記事/日 |
| 45,000 | 2020/12/13 | 21日 | ▲47.6 記事/日 |
| 46,000 | 2020/12/30 | 17日 | ▲58.8 記事/日 |
| 47,000 | 2021/1/20 | 21日 | ▼47.6 記事/日 |
| 48,000 | 2021/2/11 | 22日 | ▼45.4 記事/日 |
| 49,000 | 2021/3/8 | 25日 | ▼40 記事/日 |
| 50,000 | 2021/4/15 | 38日 | ▼26.3 記事/日 |
| 51,000 | 2021/5/26 | 41日 | ▼24.2 記事/日 |
| 52,000 | 2021/7/18 | 53日 | ▼18.9 記事/日 |
| 53,000 | 2021/8/25 | 38日 | ▲26.3 記事/日 |
| 54,000 | 2021/9/27 | 33日 | ▲30.3 記事/日 |
| 55,000 | 2021/10/28 | 31日 | ▲32.3 記事/日 |
| 56,000 | 2021/11/8 | 11日 | ▲90.9 記事/日 |
| 57,000 | 2021/12/4 | 26日 | ▼38.5 記事/日 |
| 58,000 | 2021/12/27 | 23日 | ▲43.5 記事/日 |
| 59,000 | 2022/1/26 | 30日 | ▼33.3 記事/日 |
| 60,000 | 2022/2/21 | 26日 | ▼38.5 記事/日 |
| 61,000 | 2022/2/26 | 5日 | ▲200 記事/日 |
| 62,000 | 2022/2/27 | 1日 | ▲1,000 記事/日[注 10] |
| 63,000 | 2022/3/17 | 18日 | ▼55.6 記事/日 |
| 64,000 | 2022/4/11 | 25日 | ▼40 記事/日 |
| 65,000 | 2022/5/8 | 27日 | ▼37 記事/日 |
| 66,000 | 2022/5/29 | 21日 | ▲47.6 記事/日 |
| 67,000 | 2022/6/4 | 6日 | ▲166.7 記事/日 |
| 68,000 | 2022/6/12 | 8日 | ▼125 記事/日 |
| 69,000 | 2022/6/26 | 14日 | ▼71.4 記事/日 |
| 70,000 | 2022/7/22 | 26日 | ▼38.5 記事/日 |
| 71,000 | 2022/7/24 | 2日 | ▲500 記事/日 |
| 72,000 | 2022/8/9 | 16日 | ▼62.5 記事/日 |
| 73,000 | 2022/8/24 | 15日 | ▲66.7 記事/日 |
| 74,000 | 2022/9/5 | 12日 | ▲83.3 記事/日 |
| 75,000 | 2022/9/28 | 23日 | ▼43.5 記事/日 |
| 76,000 | 2022/11/5 | 38日 | ▼26.3 記事/日 |
| 77,000 | 2022/12/3 | 28日 | ▲35.7 記事/日 |
| 78,000 | 2022/12/25 | 22日 | ▲45.5 記事/日 |
| 79,000 | 2023/1/22 | 28日 | ▼35.7 記事/日 |
| 80,000 | 2023/2/15 | 24日 | ▲41.7 記事/日 |
| 81,000 | 2023/3/5 | 18日 | ▲55.6 記事/日 |
| 82,000 | 2023/3/19 | 14日 | ▲71.4 記事/日[注 11] |
| 83,000 | 2023/4/8 | 20日 | ▼50 記事/日 |
| 84,000 | 2023/4/28 | 20日 | ―50 記事/日 |
| 85,000 | 2023/5/21 | 23日 | ▼43.5 記事/日 |
| 86,000 | 2023/6/14 | 24日 | ▼41.7 記事/日 |
| 87,000 | 2023/7/4 | 20日 | ▲50 記事/日 |
| 88,000 | 2023/7/30 | 26日 | ▼38.5 記事/日 |
| 89,000 | 2023/8/23 | 23日 | ▲43.5 記事/日 |
| 90,000 | 2023/9/5 | 13日 | ▲76.9 記事/日 |
| 91,000 | 2023/9/24 | 19日 | ▼52.6 記事/日 |
| 92,000 | 2023/10/16 | 22日 | ▼45.5 記事/日 |
| 93,000 | 2023/11/9 | 24日 | ▼41.7 記事/日 |
| 94,000 | 2023/11/24 | 15日 | ▲66.7 記事/日 |
| 95,000 | 2023/12/16 | 22日 | ▼45.5 記事/日 |
| 96,000 | 2023/12/31 | 15日 | ▲66.7 記事/日 |
| 97,000 | 2024/1/11 | 11日 | ▲90.9 記事/日 |
| 98,000 | 2024/1/24 | 13日 | ▼76.9 記事/日 |
| 99,000 | 2024/2/16 | 23日 | ▼43.5 記事/日 |
| 100,000 | 2024/3/3 | 16日 | ▲62.5 記事/日 |
| 99,000(2回目[注 12]) | 2024/4/8 | 85日[注 13] | - |
| 100,000(2回目) | 2024/4/24 | 16日 | ―62.5 記事/日 |
| 101,000 | 2024/5/16 | 23日 | ▼43.5 記事/日 |
| 102,000 | 2024/6/7 | 22日 | ▲45.5 記事/日 |
| 103,000 | 2024/6/27 | 20日 | ▲50 記事/日 |
| 104,000 | 2024/7/17 | 20日 | ―50 記事/日 |
| 105,000 | 2024/8/15 | 31日 | ▼32.3 記事/日 |
| 106,000 | 2024/9/24 | 40日 | ▼25 記事/日 |
| 107,000 | 2024/10/17 | 24日 | ▲41.7 記事/日 |
| 108,000 | 2024/11/10 | 24日 | ―41.7 記事/日 |
| 109,000 | 2024/12/6 | 26日 | ▼38.4 記事/日 |
| 110,000 | 2024/12/28 | 22日 | ▲ 45.5 記事/日 |
| 11,1000 | 2025/1/16 | 19日 | ▲ 52.6 記事/日 |
| 11,2000 | 2025/2/6 | 21日 | ▼ 47.6 記事/日 |
| 11,3000 | 2025/2/23 | 17日 | ▲ 58.8 記事/日 |
| 11,4000 | 2025/3/9 | 14日 | ▲ 71.4 記事/日 |
| 11,5000 | 2025/3/29 | 20日 | ▼ 50 記事/日 |
エンペディアの記事は指数関数的に増加しており、だいたい年に1.3倍のペースで増えている。ユーザー数の少なさに比べて記事の増加スピードが速いのには、主に2つの理由がある。1つめは、一行記事の作成が許容されているため。2つめは、ウィキペディアからの転載が盛んに行われているためである。
エンペディアとウィキペディアは同じライセンス(CC BY-SA)を用いており、記事を合法的に転載することが可能である。ただし、転載を無制限に認めると、単なる「ウィキペディアのコピペサイト」になってしまうため、一定の制限が設けられている。例外として認められているものは下記である。
ちなみに、似たような回収作業を行っているサイトとして「Everybodywiki」がある。こちらは人力ではなくbotで回収作業を行っているため、著作権侵害・プライバシーなどの問題を含む記事も構わず回収されてしまっている(エンペディアは人力作業のため、そうした記事は弾いている)。
管理者の推移[編集]

ドメイン[編集]
2023年9月26日現在、有効なエンペディアの公式サイトのドメインとしては「enpedia.rxy.jp」、「enpedia.myht.org」、「enpedia.org」[16]、「old-enpedia.rxy.jp」、「enpedia2.myht.org」が存在し、2023年9月26日現在その内「enpedia.rxy.jp」、「enpedia.myht.org」、「enpedia.org」は現エンペディア(3rd Enpedia)が表示されるように設定され、「old-enpedia.rxy.jp」と「enpedia2.myht.org」は2nd Enpediaが表示されるように設定されている。
その他[編集]
- サーバー事情
- 2013年7月18日、Yahoo!ニュースから「ふじみ野暴力団抗争事件」の記事へのリンクが張られ、アクセスが大量増加。1分当たり100回以上のアクセスが発生して、アクセス不能に陥った。当時は「過疎ペディア」真っ只中であったため、ここまでアクセスを集めることが予想されていなかった。
- その後、サーバーの最適化が着々と行われた。例えば、2015年7月15日にはYahoo!ニュースから「名古屋キャバクラ放火殺人事件」へのリンクが張られ、前回の「ふじみ野~」以上のアクセス数を集めているが、特にサーバーエラーが発生することはなかった。
- アンサイクロペディアと比較すると、アクセスはかなり快適。
- なんか時々読み込み失敗する時も一応ある。そんな時は、書いてある通りに数分待ったら大体OKである。たぶんおま環。
- 広告について
- 広告がうざいと言われる事もあるようだが[17]、広告ブロッカーを入れたり、「編集」→「プレビューを表示」ボタンを押したり、個人CSSを設定したりすることで消すことは可能。
- サーバーを運営している以上は、運営費がどうしても必要になる。ウィキペディアと違って、うざったらしい寄付は募っていないので、そのぶん広告があると思えば許容範囲であろう。
詳細は「Enpedia:広告」を参照
詳細は「自動広告が目次や基礎情報テンプレートの中に掲載されてしまう問題」を参照
- 検索について
- サイト内検索は曲者であり、合成語や文章などはうまく検索できない。
詳細は「よみもの:検索する文字列が部分一致しているはずなのにエンペディアの検索機能で出てこない条件(2024年5月14日現在)」を参照
- スパム対策
- かつてはスパム対策のため、「ReCAPTCHA」(私はロボットではありませんでお馴染みのアレ)が導入されていた。IPユーザーと新規ユーザーは投稿するたびに毎度毎度、面倒な質問をくぐり抜ける必要があった。この関門が、エンペディアの治安を高めユアペディアのような荒れ果てたサイトになることを防いでいる一方で、新規ユーザーが増えない原因なのではとも囁かれていた。
- 2024年2月7日のサーバーメンテナンス以後は、より簡単にクリアできる CloudFlare Turnstile へ置き換えられている。これでもっとユーザーが増えるかもしれないね、やったね。
- 𝕏(旧・Twitter)
- かつては rxy 氏や takumi3 氏がエンペディアを喧伝するTwitterアカウントを動かしていたが、とうの昔に更新をストップしている。
- X におけるエンペディアの評判については「#各界からの評価」の章を参照のこと。
- MediaWiki
- 「MediaWiki」というシステムを使っており、関連機能を利用できる。これにより、Wikipediaなどの類似サイト用に開発されたAPIなどを応用して Enpedia 用のものをつくれる。例えば、オプゲーがenpedia衰弱というenpediaの情報を利用したゲームを公開している。
- 英語の名称
- エンペディアの正式な英語名は「Enpedia」であるが、Google 翻訳で英語にすると「Empedia」となる問題がある。しかし、特に誰も気にしない。
存在価値[編集]
「エンペディアの存在価値をいかに評価するか」は立場によって異なる。
エンペディアは「出典(ソース)の記載が必須ではない」「独自研究を載せてもよい」「短い記事(時には一行記事)を書いてもよい」など、気軽に記事を執筆できる環境が整っている。そうした「編集者ファースト」のサイトとして捉えた場合、エンペディアには十分、存在価値があるといえるだろう。他のウィキサイトに居づらくなったユーザーが流れ着いてくる場所(通称:亡命ペディア)という一面もあり、ウィキ編集欲を満たす場所として十全に機能している。
一方、読者にとってのエンペディアはどうか。「飯塚事件」のように極端に優れた記事もあるが、ほとんどの記事は内容が不十分であり、クオリティの二極化が激しい状態といえる。日本語が読みづらい記事も、決して少なくない。とはいえ、(ウィキペディアでは特筆性を理由に削除されてしまうような)マイナーなテーマの記事が多い所はせめてもの長所であり、ニッチな調べ物で人知れず役に立っている可能性は無くはないだろう。メジャーなテーマの記事は、ウィキペディアやコトバンク、ニコニコ大百科などの既存勢力が強く、それらの価値を上回ることは容易ではない。ただし、ウィキペディアで禁止されている「利用ガイド的な記述」はエンペディアでは許されているので、その意味では読者ファーストの側面を持っていると言える。
余談になるが、ビジネスの世界には「ロングテール」という言葉がある。例えば Amazon.com は、有名な商品だけでなくマイナーな商品も大量に取り扱っている。マイナーな商品1個1個がもたらす利益はごくわずかであるが、とにかく多くの種類を取り揃えることで全体としては大きな利益を出している。同様に、エンペディアのマイナーな記事も1個1個の注目度はごくわずかであるが、幅広い大量のマイナーなテーマを取り扱うことで、全体として高い注目度を集める可能性はある。という希望的観測である。
また、「声優」と「サッカー選手」の記事が非常に多く存在するが、「モブ役しかない声優」「あまり活躍せずにすぐ引退した選手」まで網羅しているため、一個一個の記事というより全体としての「データベース」的価値はかなり高い。また、ウィキペディアと異なり、出典の無い事実や目撃情報も記載可能であり、史料的価値も高いサイトであると言える。
エンペディアは「編集者ファースト」なのか「読者ファースト」なのか、という思想の対立は黎明期から存在している。なにせ、「個人サイト」から何となく流れで発展してきたサイトなので、確固たる方向性というものが定められていない。黎明期には、管理者A(引退済み)が「800バイト以下の記事の作成を禁止する」というルールを提案し、「読者ファースト」路線を強く打ち出していたこともあった(結局、採用はされなかったが)。最近は、品質二の次で記事を書きまくるイベント「ミヤコ様スーパースプリント」(2023年春・秋)が開催されるなど、「編集者ファースト」の風潮が強まっている。しかしまぁ、ほとんどのユーザーは「どちらか一方だけ」ということはなく「両方の気持ち」を半々ぐらいに持って活動しているのであろう、知らんけど。
ちなみに、アクセス統計のアーカイブを見ると、1日あたりのユニークビジター数は2018年から2023年までは4,000~5,000人程度を維持しつづけている[注 14]。エンペディアのアクティブユーザーが数千人もいるわけはないので[注 15]、内輪の編集者ではない外部の閲覧者もちゃんと存在しているようである。日による浮き沈みがほとんど無く、毎日4,000~5,000人程度を維持しつづけていることを踏まえると、存在価値はそれなりにあるといえるのではないだろうか。訪れた閲覧者が満足したかは別である。
他のウィキサイトとの関係[編集]
- 総論
- 他のウィキサイトにおいても、エンペディアについて解説する記事が数多く立項されている。これは、ウィキサイト界隈におけるエンペディアの知名度の高さを証左すると言えるだろう。
「インターネット百科事典におけるエンペディアに関する記事」も参照
- ウィキペディアとの関係
- 直接的な関係はない。ただし、ウィキペディアの方針に合わない記事が、エンペディアに転載(エスケープ転載)されることは多い。
- 逆に、エンペディアからウィキペディアへの転載はそう多くないが、無断転載の疑いのある記事が一部ある。
- 日本語以外のウィキペディアでは、エンペディアが参考文献として挙げられることがある。それでいいのか、ウィキペディア。
- また、ウィキペディアでは、エンペディアの記事が白紙保護となっている。
「Enpediaの記事がWikipediaに逆転載された例」、「エンペディアからウィキペディアへの移入」も参照
- +Wikipediaには{{User Enpedia}}と言われるテンプレートがYuki-cy氏の利用者サブページにある。が、左に書いてある文字が「ヤ」である。
- チャクウィキとの関係
- 直接的な関係は無いが、両方にアカウントを持っているユーザーは存在する。
- ウィキペディアにはエンペディアの記事は無いが[注 16]、チャクウィキにはエンペディアの記事が存在するので、いちおう語るに値するサイトとして見なされている模様。[18]
- チャクウィキ独特の箇条書きでいろいろと書かれているが、少々時系列が分かりにくいような気がしないでもない。
- ウィークペディアとの関係
- 似通ったサイトとして、運営方針が曖昧かつ自由気ままな「ウィークペディア」というサイトが存在したが、現在は閉鎖している。
- エンペディアと同様に、自由度の高い実験的なサイトを銘打って設立されたもの。
- 同サイトの公式文書では「エンペディアと似て非なるもの」という記述が散見された。[19]
- ユアペディアとの関係
- ユアペディア内には、エンペディアについて書いた記事がいくつかあるが、情報はちょっと古め。結構、皮肉られている?ような感じもするが、エンペディア黎明期の記事は輝いていた、などと評価する記載もあったりする。「プログラマリオ」および「地雷鉄」の記事では、エンペディアは「ザル法」と評されている。
- また、エンペディアからユアペディアに無断転載された記事も多い。転載した人は悔い改めて。
- なんかレスポンスが遅い?ので、エンペディアがだいぶ快適な環境なんだなと気付かされる。
- 一方、「エンペディア (実態)」は誹謗中傷となっている。
- タヌキぺディアとの関係
- 直接的な関係は無い。設立者は「想像地図研究所」と言う架空の団体が設立したものだ。
- Wikipediaでは自分の創作物の記事を書くことが禁止されていいるが、タヌキぺディアではそういった記事を書くWikiサイトなので当サイト(Enpedia)に似ている。但し、地球上を舞台とした空想世界の記事を書くことはできないのでこのサイトで書く事をおすすめする。
- マイペディアとの関係
- 直接的な関係はないが。2024年夏ごろからこちらからあちらへ移住したものが多い。
- Enpediaで無期限ブロックされた利用者も移住している。[注 17]
- そのせいかマイペディアでのエンペディアの記事はかなり辛口な仕上がりになっていたが、Imoyokan-scratch氏によって、誹謗中傷の可能性がある記述として版指定削除・除去された。Internet Archiveから古い内容を確認することができる[1]。また、エンペディアンの記事についても非難調で書かれたものがある。
- また、エンペディアと同じくゆるく、一行記事も許される。
主要ウィキサイトのお互いの評価[編集]
各界からの評価[編集]
SNSでの評判[編集]
ツイッターで「エンペディア」「enpedia」と検索すると、9割は鉄道界隈の話題、0.5割は「飯塚事件」の話題、0.5割はその他の記事の話題である(2023年冬現在)。鉄道界隈からの注目度が高いのは残念ながら当然として、「飯塚事件」の注目度の高さは特筆に値する。
グローバル人気!?[編集]
エンペディアがグローバル人気のサイトであることは、疑う余地のない事実である。
えー...そこの君、疑う余地のない事実であるので、疑わないように。
AIも認める専門性の高さ[編集]
高精度の回答で話題のAIチャットボット「ChatGPT」に、エンペディアとウィキペディアの違いについて尋ねたところ、次のような回答が返ってきた。
エンペディアとウィキペディアは、基本的に同じものです。ウィキペディアはオープンソースの百科事典であり、誰でも記事を投稿したり編集することができます。一方、エンペディアは専門家や専門家が作成した、より専門的な情報を含む百科事典です。
ついに、AIも認める時代が来た[注 20]。今こそ参加しよう、エンペディアに。
ちなみにChatGPT以外にもPerplexity AIも別の形で認めている模様。その結果は実際のEnpediaとWikipediaの違いにより近いと思われる。めんどくさいし、長くなるのでここには書かないが、詳しく知りたい方は https://www.perplexity.ai から「ウィキペディアとエンペディアの違い」と質問。
ギャラリー[編集]
10万記事達成を記念したアスキーアート
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠁⠂⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠍⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡑⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⡗⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠐⢚⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⠂⠂⠂⢄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⠂⣠⣴⣦⣤⣦⡄⢀⣀⣠⣴⣾⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠁⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⣀⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠌⠠⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠏⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣴⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠡⠸⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⣠⣤⣤⣶⣿⣿⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡤⢤⣀⡀⠠⣤⣤⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣤⣤⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⠉⠂⠘⠻⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠩⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣤⣤⣄⣀⣤⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣴⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠈⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠍⠅⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⡟⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡁⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣦⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡀⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢹⡟⠿⡿⠷⠂⠂⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣮⡐⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢢⡄⣀⢈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣤⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠂⣀⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠞⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠓⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⣸⣿⣷⣄⠂⠂⢀⣤⣤⡀⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣇⣀⣀⣤⣶⣶⡄⢀⡀⢈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠚⠿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠲⣶⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡘⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣢⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⢐⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣷⣿⣿⣿⣶⣶⣄⣀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⠐⠛⠃⠂⢀⠂⠠⠂⠁⠂⣠⣄⠈⠻⣿⣿⡿⠟⠛⠻⢿⣿⣷⠈⢄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣤⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠍⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⣀⠂⠂⠂⠂⢇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠋⣤⠄⠂⡼⣿⡿⠇⠘⠿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠻⠿⣷⣈⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠏⠂⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣜⢿⣄⠂⠂⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠼⢉⣉⠂⠻⠽⢿⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢽⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⢟⠉⠁⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡽⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⢸⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⠋⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⠄⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣎⠃⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⡟⢣⣾⢳⣴⡀⠂⠂⢀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡎⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⡏⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣾⣿⣿⣿⣿⡟⠋⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠂⠂⠂⢳⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⢶⣂⠈⡾⠂⠂⠂⠘⢛⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡀⠂⠂⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢁⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠉⠛⢿⣿⣿⣿⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⢻⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠿⠡⠆⠂⠂⢀⡀⠘⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⢀⣀⠂⠂⡀⣤⡟⣲⣾⣿⣿⣿⣷⣏⣁⣴⣦⣤⣤⣤⣤⣾⣿⣿⣶⣶⣶⣤⣦⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⠂⠂⠂⠈⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠯⠡⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣴⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠻⣿⣷⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣤⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⢻⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣄⣤⡀⠠⠄⠂⢀⣤⡀⠂⠂⢀⣀⣠⣿⣷⣿⣃⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⣠⣶⣶⣶⣤⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⠃⠂⠂⣶⣀⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣀⠂⠈⣷⣴⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⠂⢀⣠⣴⣾⣷⣿⣿⣿⡆⢀⡔⠉⠉⣩⣤⣄⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠉⠿⠂⠁⠛⠛⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠐⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣧⠘⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣷⠂⢸⣿⣆⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠓⢟⣁⠂⠂⣼⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣅⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⣋⠹⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠋⡀⠘⠿⣿⣿⣿⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⡈⠟⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠂⠼⢛⣿⣿⣶⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢯⣅⣀⡟⠁⡄⢀⣴⣲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣠⣤⣤⣤⣶⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣴⣦⠄⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠠⠂⠘⣻⣿⣿⣤⠂⠂⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣼⣿⣿⣿⠟⠉⠙⢿⣿⣿⡇⠂⠛⠿⡽⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⠿⢧⠘⠻⣿⣿⣿⣿⠯⢧⣤⣾⣿⡿⣿⣵⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡤⠤⣽⢏⣁⣸⢥⣌⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠻⠛⠛⠋⠉⠉⠩⣯⣭⣭⣭⣉⣥⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠯⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⢻⣿⡿⠛⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⠙⠛⠁⢴⣾⣯⡉⡠⠜⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢿⣿⣤⡦⠈⠉⠂⠂⠂⠂⠿⠟⠛⠁⠁⠂⠂⠈⠉⠂⠈⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣭⣿⣼⡶⢾⣿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠈⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠁⠂⠂⠂⠰⣶⣦⣤⣼⣷⣾⣿⣿⣿⠟⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣦⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣟⣛⡳⣾⣛⢿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡛⢻⣿⣼⡏⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⡀⣾⣿⣿⣿⡿⠟⠉⣀⢸⣿⢗⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⠛⠣⡌⠻⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣻⣯⣟⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠿⣿⣯⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠈⠁⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⣀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⢻⣿⣀⣠⢠⣔⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠻⠿⣿⡉⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢧⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠻⣷⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⠈⢻⣶⣟⣧⡼⠛⡁⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠤⠂⠂⠋⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠌⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠡⠁⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠣⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠜⢿⣷⠶⡤⠂⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⣀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣇⣀⡀⠄⠻⠾⠇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⢻⠃⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⢿⣿⣿⣷⣶⣤⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡞⠛⠁⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣃⠐⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠐⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣤⣷⡀⠂⠂⠈⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠥⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠉⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡌⠂⣯⠁⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣅⣨⡀⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠡⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠉⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⡘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣩⣿⣯⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠈⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠶⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⡟⡿⣿⣁⠉⢉⠹⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣷⣮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠉⠂⣿⣿⣿⣿⣿⢹⣽⣿⣾⡯⣨⣿⣾⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠌⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⢀⣸⣇⢸⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣿⡏⣄⡈⠻⣿⣿⣿⣿⣟⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣿⣿⣿⣿⢿⠿⣋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⡛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⠾⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⡜⠉⠖⠻⢿⣦⣍⠙⢿⣟⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⡿⠿⣻⣿⠒⣢⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣘⣿⡿⢟⣉⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣻⡿⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣤⡴⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠉⠉⠛⠻⢿⣿⣶⣦⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠙⠛⠿⣿⣷⣶⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣶⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠿⢿⡿⠿⠛⠋⠁⠈⠉⠉⠉⠉⠙⠻⠿⣿⣿⣷⣿⣾⣷⠂⠻⣿⠶⣤⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣼⣿⠿⣿⠙⠦⢸⣿⣿⣿⣿⡷⠒⠒⠋⠁⠉⠉⠉⠉⠉⠛⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡶⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠙⠛⠿⢿⣿⣶⣦⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⢿⣿⣿⣦⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠠⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⢿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⣿⣿⣿⣧⣆⢿⢶⢾⣷⣽⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣭⣿⣿⣿⡿⢧⣬⣽⡗⢴⢠⡘⠿⠂⠂⢹⣿⡿⠛⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠏⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⢿⣿⣿⣶⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠨⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⢀⡤⢀⣤⣤⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣶⣶⣿⣶⣶⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠓⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣴⣶⣾⣷⣶⣦⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣯⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⣶⣶⣿⣷⣶⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣮⣉⣾⣿⣷⣦⣤⢿⣿⣿⣿⡿⣿⡿⠟⠽⣇⠉⠻⢿⠛⢶⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠋⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣤⣶⣶⣿⣶⣶⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣶⣾⣿⣶⣦⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠠⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣶⠶⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⢿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⣿⣮⣿⣿⡛⠟⠢⠈⠂⠈⠁⠈⠁⠂⠂⠈⠁⠂⠂⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠴⠛⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣤⣴⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣷⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠛⠛⠻⢿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠛⠛⠻⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠻⠛⠻⢿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠛⠛⠻⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠘⢿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣶⣶⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣄⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⡀⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⠁⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣼⣿⢿⣿⣿⣿⢿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣤⣴⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢣⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠋⠉⣿⣿⠿⠿⠋⠁⠂⠳⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣶⣦⣤⣤⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣲⣿⣆⣀⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢇⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠌⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠁⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠃⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⡀⠉⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠆⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢡⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡿⠩⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣤⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⣀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣁⡀⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠛⠛⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣀⠂⠈⠉⠛⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⣶⣾⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠓⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠈⠙⠋⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠙⠛⣗⣦⣀⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⢠⣤⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣥⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣄⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠙⠿⠢⢀⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡿⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠣⠠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠙⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠙⠻⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠂⠁⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⣴⣶⣶⣶⣶⣦⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠼⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⡯⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣥⣀⠁⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠓⠦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠂⢽⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⡁⢀⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⢿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣶⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠈⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⡇⡀⠂⠂⠂⢀⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠁⠂⠂⠂⠉⠈⢉⣻⣿⣿⣷⣂⣀⣀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢂⣺⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⡟⠄⢀⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠿⠛⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠡⢻⣿⣿⣿ ⣿⣿⡟⣡⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠠⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠛⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿ ⠏⣡⣴⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠛⠛⠛⠛⠟⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿ ⢸⣿⡿⠿⠛⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠙⠛⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣻⣿⣿⡯⠂⠚⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⢩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢐⢘⣿⣿ ⢺⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⠛⠛⠋⠂⠘⠛⠛⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣄⣷⣦⣤⣴⣶⣶⣤⣶⡦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⢻⣿⠘⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠒⢿⣿ ⣦⡤⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠋⠉⠉⠛⠛⠿⠿⠿⠿⢿⠿⣿⠷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠛⣛⣻⣿⣿⣋⣉⠛⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⢿⣿⠿⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⡏⣿⣤⠹⣧⡇⠈⠃⢿⣽⡅⠙⠿⠟⠋⢁⣾⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠙⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠠⢸⣿ ⣿⠡⠠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠙⠓⠒⠶⠶⠶⠶⠦⠤⢤⣤⣄⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡸⠿⠷⠧⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠛⠓⠂⣠⣤⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡝⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠨⣿ ⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣶⣶⣦⣤⣤⣤⣤⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⠆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠅⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠙⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⠋⠂⢹⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⣹ ⡃⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣶⡇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠳⠖⢰⣿⢿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢚ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡏⠛⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡟⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⡄⠈⠃⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⠟⠛⠋⠂⠂⢠⣧⡀⣾⣇⣠⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠉⠛⠿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⡿⠟⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠟⠂⠃⠠⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⢀⠞⠉⠄⠂⠂⠂⢠⣿⣄⣠⣮⠉⢹⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠅⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠻⢿⡯⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠂⠄⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣀⣈⢠⠂⠂⠂⠂⠂⠾⣿⣿⣿⣽⣄⣼⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⠈⠚⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡠⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⡗⠂⠓⡴⠂⣿⣿⣿⣿⣼⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⢦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣀⡀⠠⣤⣄⣦⣀⠂⠂⣠⣤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⢀⡿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⠂⠂⠃⠂⣨⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡶⠂⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣁⣈⣷⡄⢻⣿⣿⠟⣦⣤⢸⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⠃⢰⠃⠂⣠⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⢀⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠞⣋⡀⠂⠘⢿⣷⣶⠶⠦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣈⡹⠟⢠⣾⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠻⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠋⠉⠂⠂⠻⣶⣯⠥⣶⡾⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣯⠁⡌⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠁⠂⠙⠷⠆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⢉⣩⡜⠋⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡏⠙⠛⠛⠿⢿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡁⢸⣿⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⢰⡷⢲⠆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣻⣾⣟⣿⣇⢹⣿⣿⣻⡃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣷⣾⣶⣴⣶⣌⣁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣼⣿⣿⣿⣷⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⠉⠻⠿⠿⠃⢸⣿⢟⣩⣧⣬⢻⡿⠿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⣠⡶⣶⣤⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡆⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠋⠻⢿⡷⠘⠇⠶⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⢿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠟⠙⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡡⣀⠂⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠁⠂⠂⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⢹⡿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⠟⠂⠂⠘⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣦⣹⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣤⣤⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠻⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣧⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣰⣶⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⢐⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⡇⢠⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⣿⡿⠛⠟⠛⠛⢛⣋⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢙⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣇⣠⣶⣦⣤⣀⣀⣀⣀⣀⡀⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⡿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢳⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣾⡿⠉⠉⠓⠢⣤⣄⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠙⠿⠿⠁⠂⠐⡋⠂⣤⡤⣻⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣠⡀⠂⠂⠂⠂⠸⣿⠷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣥⣾⣿⣯⣿⣷⣦⣤⣄⣤⣤⣿⣿⣿⣿⣦⠂⣳⣴⡄⣄⣹⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢷⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⣹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⡛⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢽⣤⡀⠂⠉⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⢻⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣥⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣷⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠿⡿⣿⡿⠿⠿⣿⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⣿⣄⠂⢤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣦⣤⣄⣀⢀⣀⣀⣉⣀⣌⠂⠈⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣦⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠘⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠛⠛⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣃⣾⡟⠟⣻⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⣿⣿⣶⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠿⣿⣷⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠈⠻⢿⣿⣷⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢽⣿⣿⣿⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⢿⣿⣷⣄⣻⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠉⠉⠉⠉⠉⠋⠋⠂⠂⠈⠛⠉⠁⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⡀⠂⠂⢸⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⣦⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣦⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢘⣿⣿⣿⣿⣷⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠈⠈⠻⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣏⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣿⣿⣷⡄⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣶⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣦⣄⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣶⣤⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣷⣦⣤⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣄⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣶⣤⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠉⠂⠂⠉⠏⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠛⠛⠋⠻⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡀⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠿⠿⠿⠿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⡿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠷⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⠛⠛⠉⠂⠂⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠙⠋⠉⠛⠋⠉⠉⠁⠂⠂⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡛⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠛⠛⠛⠻⠿⠟⠛⠛⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠛⠛⠻⠿⠿⠟⠛⠛⠋⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡉⠳⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠛⠛⠻⠿⠿⠿⠟⠛⠛⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⢿⣿⣿⣿⡿⠃ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠊⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣆⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠙⣦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠉⠉⠙⠛⠋⠉⠙⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡈⠳⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⠴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢠⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⢻⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣷⣦⣄⡀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⢻⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢺⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠆⠂⠂⠂⣀⣬⣉⣿⣿⣶⣦⡀⢀⣀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⢢⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⢿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠿⠃⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⢿⠃⠂⠂⠂⢨⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠅⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠄⢀⣠⡴⠆⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣴⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣲⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠂⠂⢀⠸⠿⠋⠂⠂⠂⢘⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠙⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠤⠶⠒⠂⣀⠠⢄⣺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡾⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠛⠙⠉⠉⠙⠛⠛⠋⠙⠉⠛⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣶⣦⡶⠶⠉⠛⠉⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⢀⣶⣤⡦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⣼⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡿⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠂⢄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣤⣤⠾⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠛⠛⠁⠉⠉⠛⠛⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣷⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⣸⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠉⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠛⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠙⠛⠿⠟⠿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣤⣄⡀⠂⢀⣤⣴⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠸⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⢱⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⠂⠂⡤⢒⣤⣠⣄⣀⡈⣀⡀⢒⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠈⢷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠳⣾⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣶⣾⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠰⢷⣆⡀⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣾⣦⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠘⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣞⡰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣤⣀⣴⣦⣾⣿⣿⣷⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣾⣶⣤⣶⣶⣦⣤⣄⣹⣦⡤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣰⠏⢀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣶⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⡾⢣⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢹⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⠋⣰⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠛⠋⠉⠉⠉⠉⠛⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠁⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠈⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣉⠁⢠⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠙⠛⠛⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠸⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⠿⠿⢿⣾⣿⣦⣤⣁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣦⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⡿⠁⠂⣠⣿⣿⣾⣿⣿⣅⣴⣦⣤⣀⣀⣀⠂⢀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣷⡄⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣁⣀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣏⣠⣤⣶⣦⣤⣤⣄⣠⣾⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠇⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⣾⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢶⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢹⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠛⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠛⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⠂⢠⡿⠟⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢋⡁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀⣸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢿⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⢻⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠻⣿⣿⣉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⡄⠂⠂⠂⠂⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠸⠿⠿⠟⠂⠂⢀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣤⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠉⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢻⣿⠿⠿⠛⠉⠉⣻⣿⡟⠉⠉⠉⢹⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠉⠉⠉⠉⠙⠛⠛⢿⣿⣿⣿⡀⢃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⡀⠂⠂⠂⢠⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⢠⣴⣶⣶⣦⠂⠂⠈⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⣿⣯⣀⣀⡀⠂⠂⢀⣤⣤⣀⣀⣰⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣶⣶⣄⠂⠂⠂⠹⣿⣶⡀⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣤⣶⣶⣶⣄⠂⠈⢻⣷⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣶⣶⣶⣄⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣶⣶⣶⣦⠂⠂⠙⣿⣷⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⡿⠉⢀⣀⣄⣀⠂⠂⠂⠙⣿⣶⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠟⠁⢀⣀⣄⣀⠂⠂⠂⠹⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡆⠂⢠⡀⠂⠂⠂⣠⣶⣾⣿⣿⣧⠂⣤⠂⠂⢀⣤⣶⣿⣿⣿⣀⠂⠂⠂⢀⣴⣶⣶⣶⣄⠂⠉⢿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⠏⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⠃⠂⢀⣴⣶⣶⣶⣄⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣷⠈⠂⠂⠂⠂⣠⣶⣶⣶⣄⠂⠂⠹⣿⣷⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⠏⠂⠂⠂⠂⢠⣷⣦⣄⠂⠂⠂⢀⣴⣶⣿⣿⣿⡄⢠⡄⠂⠂⣠⣴⣾⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⠿⠁⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⣾⣦⠂⠂⠂⠟⢀⣴⣦⣀⣀⣼⣿⣿⣿⢿⡇⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⣿⡄⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⡿⠛⠁⠂⠂⢠⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⠟⠛⠁⠂⠂⢹⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⡿⠛⠛⠂⠂⢿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⠟⠛⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡀⠂⠂⠂⣿⡄⠂⠂⠈⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠘⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⣷⡀⠂⠂⠈⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡄⠂⠂⠂⢸⣧⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠁⠂⠘⠳⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡿⠿⠃⠂⠙⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣷⣶⣿⡆⠂⠂⠘⠃⢠⣶⣦⣀⣠⣾⣿⣿⡟⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⢸⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⠿⠛⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⣾⡆⠂⠂⠘⠃⢠⣶⣦⣀⣠⣾⣿⣿⡿⠆⠂⠂⠘⣿⣿⣿⠿⠟⠁⠘⠇⠂⢰⣿⣿⣿⡿⠿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⢀⣰⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠙⠛⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⡿⠿⢿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠉⠉⠉⠉⠂⠂⠙⠃⠂⠂⢸⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⢀⣤⣾⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠙⠃⠂⠂⠂⣾⣿⣿⡿⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠙⠃⠂⠂⢠⣿⣿⣿⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠈⠛⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⣸⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠙⠃⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣉⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋⢽⣿⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡏⠂⢀⣤⠾⠛⠉⠻⢿⠿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠙⠻⣷⣄⠂⠂⠂⠈⢿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠉⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠂⠂⠂⠙⠛⠛⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣥⠖⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⢶⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣧⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⣴⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣶⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⡿⡟⠛⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡀⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣠⣴⡆⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠟⠃⠂⠂⠂⢢⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣤⣴⡆⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡄⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠤⠂⠂⠂⠂⣀⣤⣶⡆⠂⠂⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣧⠂⠂⣸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠻⣷⣦⡀⠂⠂⠈⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⠇⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡇⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⡀⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⠃⠂⠂⢠⣶⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⠂⢠⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠅⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⡿⠛⠁⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡟⠃⠘⠁⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⠂⠂⠂⢹⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⡟⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣧⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⢸⣿⣿⣿⡇⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⠟⠋⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⠇⠂⣼⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣄⡀⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣀⠂⠂⠠⣶⣶⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⢰⣿⣿⣿⡏⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⡄⠂⠂⢿⣿⣿⠟⠉⢹⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⣸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⣸⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄ ⡐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⣷⠂⠂⠂⢠⡖⠻⠟⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⡷⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⡇⠂⠂⠙⢿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⡿⠂⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⡄⠂⠈⠛⠁⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠂⠘⢿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⢿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ ⡆⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠆⠂⣀⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠁⠂⣀⣤⣄⠂⠂⠈⢁⣠⣤⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠛⣦⣀⣀⣀⣠⣤⣤⡀⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣴⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠙⢳⣄⣀⠂⠂⠂⠂⢄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣴⣾⣿⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⣣⣀⣀⠂⠂⠂⠠⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣴⣿⣿⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠉⠓⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠉⠂⢀⣀⣤⡀⠂⠂⠉⢁⣤⣠⣤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⢻⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠛⣇⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠛⣧⣀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⢻⣄⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠛⣤⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠃⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⢠⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣴⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠉⠂⠂⠂⠂⠉⠛⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡀⠂⠂⠉⠛⠛⠉⠂⢀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⠂⠂⠂⠉⠉⠂⢀⣀⣤⡀⠂⠂⠉⢁⣤⣤⣤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⢻⣄⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣲ ⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠈⠂⣿⣯⣤⣶⣶⣾⣿⣷⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⢴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠂⠙⠿⠿⠏⠁⠘⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⡿⠃⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠈⠻⣷⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠙⢿⣶⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠂⠂⠂⠂⢿⣶⣶⣶⣶⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣾⣿⣿⣿⣿⡇⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠐⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠹⣿⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠂⣼ ⣿⡬⠠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠿⠿⣿⠿⠿⠟⠉⠂⠙⠻⠿⠿⠟⠋⠂⠈⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠿⠿⠿⠿⠟⠋⠂⠂⠈⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠻⠿⠿⠿⠿⠟⠋⠁⠂⠂⠂⠈⠛⠛⡟⠛⠛⠛⠛⠛⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⠿⠿⣿⣿⠿⠟⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠛⠻⠿⠿⠿⠿⠿⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠿⢿⡿⠿⠿⠛⠉⠂⠙⠻⠿⠿⠛⠉⠂⠈⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠁⠂⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠋⠂⠈⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠂⠂⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠁⠂⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠿⠿⠟⠃⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠙⠻⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠛⠉⠂⠙⠿⠿⠿⠛⠉⠂⠈⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢤⣿ ⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⠿⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣠⣴⣿⣿⣦⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣶⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢸⣿ ⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⠟⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢳⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⡀⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⢀⣼⣿ ⣿⣿⣂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣀⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣐⣿⣿ ⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠹⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿ ⣿⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠙⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠋⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⢠⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣷⠁⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠿⠟⠛⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠿⠿⠛⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣼⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⡏⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣆⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡂⣲⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠼⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡌⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣆⡀⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣧⣤⣶⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⡝⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤⡀⣀⣼⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⠏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢳⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡈⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠂⠂⠉⠙⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⢐⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⠿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠃⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢦⣶⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⢇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⣿⣇⣀⠂⠂⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡐⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡂⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣶⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠚⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣷⣾⡟⠂⠂⠂⠐⠂⢀⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠰⡀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⣿⡆⠂⠂⠂⠂⣠⣀⣾⣾⣿⣿⣿⣿⣦⣤⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣟⠂⠂⠂⡴⠂⠂⠈⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠘⣜⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡅⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡧⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣄⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠛⠿⢿⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢀⡤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⠇⠂⠂⢸⡌⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡌⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠻⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠅⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣯⠂⠂⠂⠂⢱⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣷⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣟⠂⠂⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⢀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠂⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡤⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠹⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⡀⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡗⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠙⠛⠟⠛⠛⠛⠛⠛⠋⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⡿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠃⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣿⡿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠛⠓⠒⠚⢦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣤⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣀⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⡟⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⣿⣿⡇⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠃⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⢐⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⠿⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⠟⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⣿⠧⢠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄⠄⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡅⠡⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⡀⣠⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠟⠋⠂⠉⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠿⢿⣿⣿⣦⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣖⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠻⢿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⣿⣧⣤⠿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⡷⠴⣿⣿⣦⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣆⣠⣶⣤⣄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠌⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⠿⠟⠉⠁⠙⠻⢷⣦⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣖⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢹⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠻⣧⣠⣿⣷⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠂⣲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣷⣀⣠⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠉⠉⠻⣿⣷⡄⠂⣀⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⠠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢻⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⢿⣾⣿⣿⣷⣤⡀⢀⣤⡀⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣿⣿⣿⡗⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄⠄⣬⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⡾⠗⠾⠟⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠉⠛⠿⠿⠿⢿⣿⣷⣦⡀⠂⠂⠈⢿⣿⣿⣿⣇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡀⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠘⠻⢿⣿⣷⣄⡀⠈⠻⠿⣿⣿⡆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡔⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⢿⣿⣶⣄⠂⠘⢿⣿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⣀⣲⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢿⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠛⣿⣿⣷⡀⠂⠛⠻⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣥⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠙⣿⣿⣷⣦⣤⣿⣆⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣬⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠡⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣀⠂⣠⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠻⠟⠛⠛⠿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠌⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⣿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⢿⣿⡟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠊⣻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠐⡐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢻⣧⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⡿⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡜⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠛⠿⣿⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡞⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣄⠥⠠⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢸⣷⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣰⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢿⡇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⠟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⢀⢈⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣐⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣠⡿⠛⠋⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⠻⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⣴⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡌⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢳⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⠂⢠⣾⠟⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠄⢥⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⠟⢠⣿⠃⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⢈⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣐⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢠⣿⠂⠈⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢃⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣆⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⠂⠂⠂⠂⠂⣶⣶⣴⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⠒⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠐⣧⠂⠂⠂⠂⢠⣿⣿⣿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡤⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠹⡄⠂⠂⠂⢸⣿⣿⡿⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠠⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⡠⠄⠄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠸⣇⠂⠂⠂⣽⣿⡟⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢌⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⢀⢀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣿⡀⠂⢸⣿⣿⠇⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⡀⣡⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⢀⣀⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣽⡇⠂⢐⣿⡏⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢀⢀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠈⠉⠂⠈⠉⠁⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⢰⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧⠂⠅⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
脚注[編集]
注記[編集]
- ↑ 漢字表記の「百科事典擬き」は使われない。
- ↑ 「アンサイクロペディアやウィキペディアから追放された人々が行きつくサイト」という設定だった。
- ↑ 正確には「チェックユーザー」はスタッフの権限ではないが、現時点ではスタッフが実質的に兼任している。「Enpedia:チェックユーザー#主なチェックユーザー(利用者調査者)」参照のこと。
- ↑ 無料のレンタルサービスであるマイサイト ユーザーズ 2.0によるもの
- ↑ ただし、旧エンペディアのオレリ氏の利用者ページでは「2009年8月5日」に設立と記載されている。真相やいかに。
- ↑ 旧エンペディアから記事のインポートが始まった2012年12月26日より
- ↑ 11,000~16,000までは情報無し
- ↑ 33,000は情報無し
- ↑ 37,000は情報無し
- ↑ サッカー関連の記事の大量立項による
- ↑ 第一回ミヤコ様スーパースプリントの影響とみられる
- ↑ フォーラムでの議論に伴い、著作権上問題のあった約3000記事が大量削除されたことによる
- ↑ 98,000項目時点から
- ↑ ちなみに、1日あたりのユニークビジター数が最大だったのは、2019年12月13日の 24,530 人。
- ↑ 2025年1月時点での「活動中の利用者」は170人前後。
- ↑ 立項されても基本削除される模様(jawp:ノート:エンペディア)。
- ↑ 例えば、トキノや天照皇女など
- ↑ なお、塞がれるもよう
- ↑ ネタバレを行うとスパムアカウントである。
- ↑
エンサイクロペディアと間違えたのだろう、というのは内緒
出典[編集]
- ↑ Enpedia:エンペディアについて
- ↑ Enpedia:旧エンペディアについて
- ↑ 以下の位置に戻る: a b c 2nd:Enpedia:スタッフ/旧制度
- ↑ http://myht.org/modules/d3forum/index.php?topic_id=409
- ↑ 2nd:特別:投稿記録/オレリ
- ↑ 特別:投稿記録/オレリ
- ↑ Enpedia:スタッフ/第2次
- ↑ 2nd:Enpedia:運営管理権限に関する全権移譲宣言
- ↑ テンプレート:記念記事
- ↑ Enpedia:お知らせ/サーバーメンテナンス#2013-11-09
- ↑ フォーラム:アクセスカウンタの無効化
- ↑ フォーラム:IPv6対応について
- ↑ 「フォーラム:自動広告への切り替えについて」参照。
- ↑ 利用者:篠田陽司/Enpedia (任意団体)
- ↑ フォーラム:書きかけテンプレートの廃止について
- ↑ 利用者:篠田陽司/Enpedia (任意団体)#2019年度下期
- ↑ 利用者・トーク:エンペディアは広告がうざいゴミサイト
- ↑ エンペディア - chakuwiki
- ↑ Weekpedia:ウィークペディアは何でないか(リンク切れ)、Weekpedia:Weekpediaについて(リンク切れ)
- ↑ Enpediaの記事がWikipediaに逆転載された例
関連項目[編集]
- Enpedia:エンペディアについて: 公式文書
- 過疎ペディア
- エンペディアン
- Enpediaあるある
- エスケープ転載
- ウィキペディア
- ウィークペディア
- 外国語版エンペディア
- エンペディアのどうでもいい与太話
- エンペディアのウィキペディア化問題
- エンプデア - Enpediaというスペルを持つ『ゼノブレイド3』のキャラクター
エンペディアの方針 |